ロビンソン・クルーソーですら、貨幣の価格と価値を理解していました
自由市場の機能において、貨幣ほど重要なものはありません。貨幣はすべての取引の半分を構成し、財やサービスの交換における価値の片側を担っています。では、貨幣の「価格」とは何を意味するのでしょうか。
市場で最も流通性の高い財が、社会における主要な交換手段、すなわち貨幣となります。この共通の基軸で価格を付けることで経済計算が可能となり、起業家はビジネスチャンスを見出し、利益を上げ、文明の発展をけん引します。
財の価格は需要と供給で決まることは自明ですが、貨幣の価格決定は一筋縄ではいきません。なぜなら、貨幣そのものの価格を測定するための勘定単位が存在しないからです。私たちはすでに貨幣で価格を表現しているため、貨幣の価値を貨幣単位で示すことができません。したがって、貨幣の購買力を別の形で示す必要があります。
人々は将来その貨幣で「何が買えるか」という期待に基づき、貨幣を売買(財やサービスと交換)します。これまで述べた通り、人は常に限界(マージナル)で選択します。ここで限界効用逓減の法則が働きます。つまり、あらゆる行動は、個人が「もっとも価値の高い目的」と「次に強く望む欲求」の間で価値判断を下すという選択によって先立ちます。限界効用逓減の法則は、財の追加単位ごとに満足度が下がる点でここにも当てはまります。
貨幣も同様です。その価値は追加単位がもたらす満足度にあります。それが食事であれ、安全であれ、将来の選択肢であれ、本質は変わりません。人々が自らの労働を貨幣と交換するのは、時間を即座に使う以上に、貨幣の購買力を重視しているからです。つまり、交換における貨幣のコストとは、差し出した現金でもたらされたであろう最大の効用のことです。リブアイステーキを得るため1時間働く人は、その食事を1時間の余暇より価値あるものと評価したことになります。
限界収益逓減の法則は、同一財の各追加単位が順に低い欲求を満たすことを示します。したがって、追加されるごとに個人が感じる価値は低下します。しかし、何が同質財かは人それぞれです。価値は主観的であり、追加される貨幣単位の効用も目的次第です。たとえば、ホットドッグだけを買いたい人にとって、「貨幣の単位」とはホットドッグ価格そのものであり、1単位分の貨幣を保有し、もう1本ホットドッグを買える状態になって初めて、「ホットドッグ用の貨幣」を追加したことになるのです。
このことは、孤島のロビンソン・クルーソーが金塊の山を見ても無価値だとみなした理由でもあります。食料も道具も住まいも買えない金は、孤立した状況では意味を持ちません。言語と同様、貨幣も最低2人以上いなければ機能しません。貨幣は究極的にはコミュニケーションの道具なのです。
インフレーションと「遊休貨幣」幻想
人々は自らの時間選好や貨幣の将来価値への期待に応じて、貯蓄、消費、投資を決定します。購買力の上昇を予想するなら貯蓄し、低下を見込むなら消費を選びます。投資家も同様に、インフレ以上のリターンを見込める資産に資金を移します。しかし、貯めていようと投資していようと、貨幣は必ず所有者に何らかのメリットをもたらします。「傍観している貨幣」ですら、不確実性を下げる明確な役割を果たしています。貨幣を保持することで、選択肢や安全性を確保する欲求が満たされているのです。
従って、「流通中の貨幣」という捉え方は誤解を生みます。貨幣は川のように流れるものではありません。常に誰かが保有し、その時点で役割を果たしています。取引は行動であり、行動は一瞬一瞬でしか起きません。したがって、「遊休貨幣」は存在しません。
貨幣が過去の価格と結びつかなければ、経済計算が不可能になります。昨年パンが1ドル、今年が1.1ドルであれば、購買力の変動が推測できます。こうした蓄積から経済的な期待値が形成されます。政府によるこの分析の代表が消費者物価指数(CPI)です。
この指数は「インフレ率」を一定の財バスケットで示すものですが、CPIは意図的に不動産、株式、美術品といった高価値資産を除外しています。なぜでしょうか? それを含めてしまうと、政府が隠したいインフレの根本的な事実――それが実際にはより広範かつ深刻である――が明るみに出てしまうからです。CPIでインフレを測るのは、本来極めて単純な事実――価格上昇は最終的に貨幣供給拡大と比例する――を覆い隠す狙いなのです。新しい貨幣の発行が、既存通貨の購買力を必ず減じます。
価格上昇をもたらす原因は、貪欲な生産者や供給網の障害ではなく、常に最終的には貨幣供給の拡大です。貨幣が増えれば購買力は下がります。新規マネーの受益者(銀行、資産保有者、政権と関係のある法人)は恩恵を受ける一方、貧困層や賃金労働者がインフレの打撃を受けています。
インフレの効果は遅れて現れ、直接的な因果関係を追いにくいため、しばしば最も陰湿な窃盗と呼ばれます。それは貯蓄を毀損し、格差を拡大させ、金融の不安定化を招きます。皮肉なことに、短期的には得をしたように見える富裕層でさえ、長期的には健全な貨幣体制の方が恩恵を受けることになります。インフレは最終的にすべての人に害を及ぼします。一時的に利益を得た人であっても例外ではありません。
貨幣の起源
貨幣の価値が購買力に由来し、しかもそれが過去の価格との比較で決まるとするなら、そもそも貨幣はどのように初期価値を得たのでしょうか。その答えは物々交換経済の時代までさかのぼります。
貨幣に進化した財は、貨幣となる前に非貨幣的な価値を持っていたはずです。当初の購買力は、何らかの非貨幣的用途が存在したからこそ生まれました。やがて交換手段という第二機能を持つと需要と価格が高まり、この財は効用価値と交換媒体という2つの異なる役割をもつようになりました。時とともに後者の役割が重要となります。
これこそがミーゼスの後退定理の核心です。貨幣は市場で自然発生し、過去の評価との結びつきを持つことをこの理論は説明します。貨幣とは国家による発明ではなく、自発的な取引の延長線上に誕生するものなのです。
金は耐久性、分割性、認知性、携帯性、希少性という「良い貨幣」の要件を満たしていたため、貨幣となりました。宝飾品や産業用途でも価値を持ち続けています。長らく銀行券は金と兌換可能な受取証として機能し、その軽さと携帯性によって金の保管・移動の問題を解決しました。しかし発行者は、実際に金庫にある以上の金券を発行できると認識し、現代までその運用は続いています。
金と銀行券のリンクが断たれると、政府や中央銀行は「無」から貨幣を生み出すことが可能となり、現在の不換通貨体制が誕生しました。この体制下で政治的に優遇された銀行は失敗しても救済される構造ができ、モラルハザード、リスク認識の歪み、システミックリスクの増大につながります。こうした損失はインフレを通じて国民の貯蓄から密かに徴収されます。
貨幣と過去価格との時間的なリンクは市場メカニズムの根幹です。これがなければ個人の経済計算は成立しません。前述した「貨幣後退定理」は、貨幣論争で見落とされがちなプラクセオロジーの洞察です。貨幣が官僚による抽象的な創作物ではなく、市場で具体的な取引によって実体化したものであることを示しています。
貨幣は自発的取引の産物であり、政治の創造物でもなければ、単なる幻想や社会契約でもありません。供給が十分限定され、交換手段として必要な条件さえ満たせば、あらゆる財が貨幣となり得ます。耐久性・携帯性・分割性・均質性・受容性が備わっていれば十分です。
もしモナリザが無限に分割可能だったなら、その一部は貨幣として流通できたでしょう。ただし、本物の断片であることを簡単に証明できる場合に限ります。
モナリザに関連して、20世紀の著名画家たちが貨幣の供給拡大が価値認識に及ぼす影響を示した逸話があります。彼らは自分のサインが特別な価値を持つことに気付き、レストランの勘定をサイン入り伝票で払ったり、サルバドール・ダリは自損事故で大破した車にもサインをして芸術品へと変えたと伝えられます。しかし、サイン付きの伝票やポスター、車の残骸が増えるにつれて一つのサインの価値は下がり、限界効用逓減の法則が示されました。量の増加は、質の低下につながったのです。
世界最大のピラミッドスキーム
不換通貨は同じ原理で動きます。貨幣供給を増やせば一単位ごとの価値が下落します。新規マネーの最初の受益者は恩恵を得る一方で、その他の人々は損を被ります。インフレは単なる経済的課題にとどまらず、道徳的な問題でもあります。経済計算を歪め、借金優遇・貯蓄軽視を助長し、最も弱い人々から富を奪います。こうして不換通貨制度は、頂点の人々を富ませ、土台の犠牲で成り立つ世界最大のピラミッドスキームとなっています。
不完全な貨幣を使い続けているのは、それが最善だからではなく、歴史的に受け継いだからに過ぎません。しかし、多くの人が「偽造不可能な健全な貨幣」が市場や人類にとって理想的だと悟れば、食物にもならない偽物の金を模した受取証に依存せず、実体ある誠実な価値を基礎とした世界づくりを志すでしょう。
健全な貨幣は、政治ではなく自発的な選択を通じ生まれます。貨幣の基本条件を満たせばどんな物も貨幣になり得ますが、文明が長期的に発展するには健全な貨幣が不可欠です。貨幣は経済ツールに留まらず、倫理的な社会制度でもあります。貨幣が腐敗すれば、貯蓄・価格・インセンティブ・信頼など経済のすべてが歪みます。けれども誠実な貨幣なら、市場は生産を調整し、希少性を伝え、倹約を奨励し、弱者を守ります。
最終的に貨幣は、単なる交換手段ではありません。時間の保存装置、信頼の記録、人類協調の普遍的な言語です。それが腐敗すれば、経済だけでなく文明そのものが壊れます。
「人間は近視眼的であり、先を見通す力は乏しい。情熱は最良の友ではなく、偏った愛着はしばしば最悪の助言者である。」

偽造:現代貨幣と不換制の虚構
市場で売れる財が貨幣へと転換し、長期的志向(低時間選好)が進歩とデフレを生み出す過程を見てきました。次は現代の貨幣の機能を詳しく見ていきましょう。近年のマイナス金利や
時間選好が常に正であるという経済原則との関係を疑問に思う方も多いでしょう。また、物価高の原因を金融緩和以外に求める報道も目にします。
現代の貨幣問題は、知れば知るほど厳しい現実を突きつけてきます。人は貨幣発行による他者からの略奪をやめられません。これを防ぐには、貨幣制度から人間そのものを排除するか、貨幣を国家から分離するしかありません。ノーベル賞経済学者フリードリッヒ・ハイエクも、これには「巧妙で迂遠な道」が必要だと考えていました。
イギリスは最初に自国通貨と金本位制を切り離した国です。第一次大戦前はほぼすべての通貨が金と交換可能であり、金は数千年かけて最も流通性の高い財として標準化されていました。ですが1971年、米国のニクソン大統領は「ドルと金の交換一時停止」を宣言し、最終的なリンクを断ちました。その目的は、ベトナム戦争の戦費調達や政権維持のためでした。
不換通貨の詳細は省きますが、今日の国家発行マネーに価値的な裏付けはなく、すべてが負債として創出されます。見かけは貨幣ですが、実際には自発的な交換から生まれる貨幣とは異なり、負債と支配の道具です。
新たなドルやユーロ、人民元は、大手銀行の新規融資によって誕生します。その貨幣は利息付きで返済されることが前提ですが、元本と共に利息分の貨幣は創造されません。結果として、システムを維持するにはさらなる借金が必要となります。現代の中央銀行は、不良銀行の救済や量的緩和といった政策で更なる貨幣供給を操作しています。
量的緩和とは、中央銀行が国債を購入するために新たな貨幣を創出し、国の借用証書(IOU)と新造マネーを交換する政策です。国債は政府が借入金を将来返済する約束ですが、その約束の裏付けは今後の課税収入です。私たちと子孫は物価上昇に晒され、地道に稼いだ資産から静かに富を奪われます。
マネーの増刷はケインズ主義という政府政策の根幹の名のもとに続きます。ケインズ派は、経済成長には支出(消費)が不可欠であり、民間が支出しない場合は国家が代行すべきだと主張します。彼らの主張では、支出1ドルが経済1ドル分の価値を生みますが、価値希釈=インフレによる実質価値低下には目を向けません。これはバスティアの「壊れた窓」の寓話そのものです。ゼロを加えることでは何の価値も増えません。
もし貨幣増刷で本当に豊かになれるなら、誰もが巨大ヨットを所有しているはずです。真の富は生産、計画、自発的な取引から生まれ、中銀バランスシートの数字を増やすことでは生まれません。実質的な進歩とは、人が将来の自分や他人と取引し、資本を蓄積し、先送りの利益を得ようと投資する行為にあります。
不換通貨の終着点
貨幣増刷は市場機能を加速させるどころか、歪めて停滞させます。購買力の持続的な低下は、経済計算や長期計画を困難にします。
不換通貨は最終的にすべて消滅します。あるものはハイパーインフレで崩壊し、また他の通貨は放棄されたり、より大きな通貨圏に吸収されます(たとえば小国通貨がユーロへ移行するなど)。しかし破綻までの間、不換通貨は価値創造者から政治権力者へ富を移転する役割を果たします。
これが18世紀のリチャード・カンティロンの名を冠したカンティロン効果です。新たな貨幣が経済へ流入すると、最初に受け取る人々が最大の恩恵を受け、インフレ前に財を購入できます。一方、末端の労働者や貯蓄者はコストを負担させられ、不換制で貧困層でいることは非常に高くつきます。
それでも政治家や中央銀行家、主流経済学者は「健全なインフレ率が必要」と繰り返します。彼らは本当はその真逆を分かっているはずです。インフレは繁栄を生まず、よくて購買力を移転し、最悪の場合、貨幣や貯蓄、協調への信頼を根本から失わせ、文明の基盤を崩します。現代の安価な財は、税・国境・インフレ・官僚制の「おかげ」ではなく、むしろそれらに逆らって実現されてきたものです。
善・悪・醜
市場メカニズムに制限がなければ、より多くの人々により低価格でより良い財が供給される傾向があります。これこそが真の進歩です。興味深いことに、プラクセオロジーは、単なる批判の道具ではなく世界への理解と感謝の枠組みでもあります。不正の深さに幻滅しがちな人も多いですが、プラクセオロジーは生産的な人々こそが繁栄の主役であることに気付かせ、政府ではないことを明示します。この見方に立てば、スーパーのレジ係や清掃員、タクシー運転手も皆、価値創造と自発的協力によって人類のニーズを満たし、彼らこそが文明の主役であることが見えてきます。
市場は「善」を生み出します。一方、政府は「悪」を生み出す傾向があります。カタラクティック競争――顧客志向の市場競争――がイノベーションの原動力であり、一方の政治競争は国家支配をめぐる争いに過ぎず、能力よりも策謀が報われます。市場では最も柔軟で適応力のある者が成功し、政治では最も抜け目のない者が台頭します。
プラクセオロジーは人間のインセンティブの本質を明らかにします。人は言葉ではなく行動を見よ、そして現状だけでなく「本来あり得た選択肢」も考慮すべきだと教えてくれます。それは、介入によって消された「見えない世界」への洞察です。
恐怖・不確実性・疑念
人間の心理は恐怖に傾きがちです。私たちは花を愛でるためではなく、脅威から生き残るために進化してきたからです。だから危機感は希望よりはるかに速く広がります。テロ、感染症、気候変動――いずれの「危機」でも、常に「さらなる政治的支配」が提唱されます。
人間行動を学べば、その理由が分かります。あらゆる個人は目的のために手段を選ぶものです。この原理は権力志向者にも当てはまります。彼らは自由と引き換えに安全を提供しますが、歴史が証明するように恐怖を原動力としたトレードオフは多くの場合、期待に応えません。こうした力学を理解することで、私たちには世界がより明確に映り、ノイズが消えていきます。
テレビを消し、自分の時間を取り戻し、資本形成や自由な時間の確保が利己的な行動ではなく、むしろ人を助ける土台であることに気付くようになります。
自己投資(スキル・貯蓄・人間関係への投資)は、社会全体の価値総量を押し上げます。分業に参加して価値を生み出し、それを自発的に行うことができます。壊れたシステムの外でより良いものを築くことこそ、最も根本的な変革です。
不換通貨を使うたび、発行者にあなたの時間を差し出していることになります。もし完全に不換通貨の利用を避けることができれば、より公正で誠実な世界の実現に貢献できます。それは容易な道ではありませんが、本当に価値あるものは簡単には得られません。
Knut Svanholm氏は、ビットコイン教育者・作家・哲学愛好家・ポッドキャスターです。本記事は、2025年5月27日にLemniscate Mediaより出版される新著『Praxeology: The Invisible Hand that Feeds You』からの抜粋です。
BM Big Readsは、ビットコインとビットコイナーに関連する最新テーマを深掘りする毎週連載です。記事内の意見は執筆者のものであり、BTC IncやBitcoin Magazineの公式見解ではありません。ご寄稿のご提案がありましたらeditor[at]bitcoinmagazine.comまでご連絡ください。
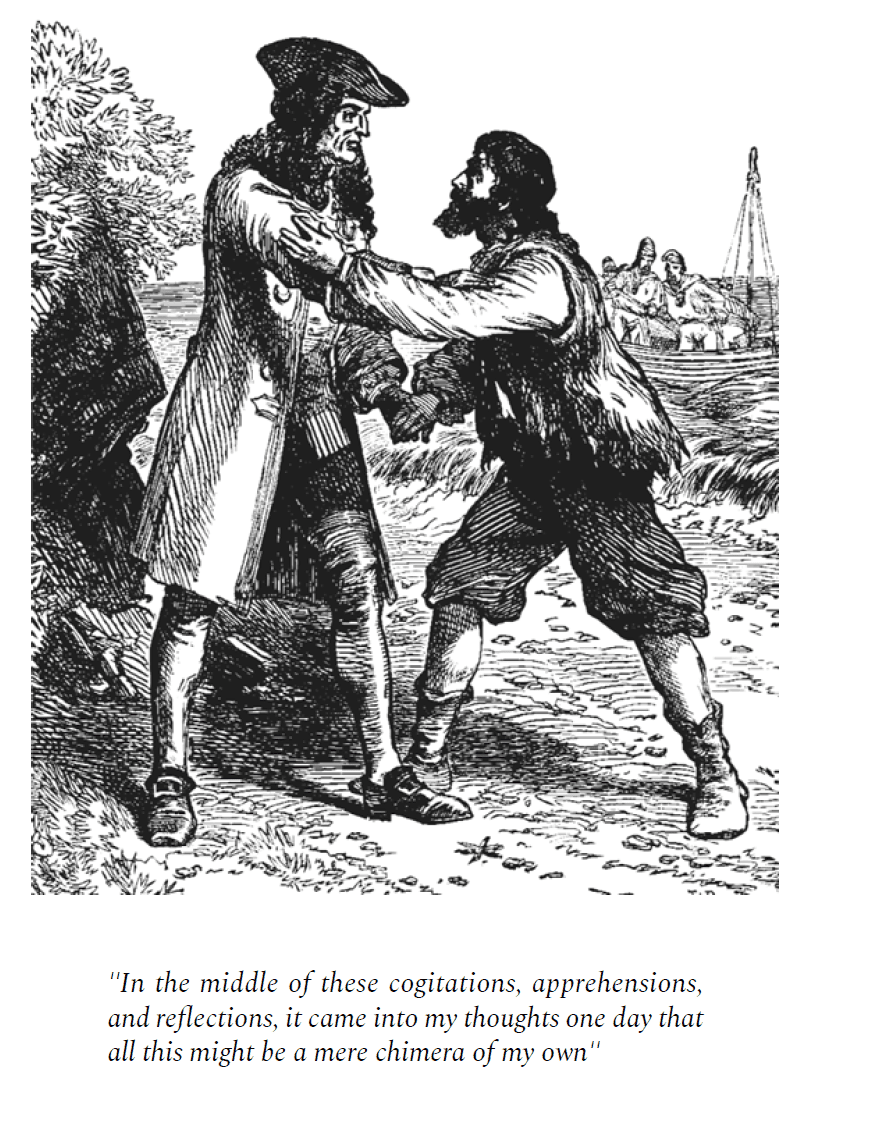
免責事項:
- 本記事は[Bitcoinmagazine]からの転載であり、著作権は原著者[Knut Svanholm]に帰属します。転載に関してご異議がございましたら、Gate Learnチームまでご連絡いただければ、迅速に対応いたします。
- 免責事項:本記事で述べられている見解・意見は執筆者自身のものであり、投資助言を意味するものではありません。
- 本記事の多言語翻訳はGate Learnチームによるものです。特段の記載がない限り、翻訳記事のコピー・配布・盗用はご遠慮ください。
関連記事


ブロックチェーンについて知っておくべきことすべて

ステーブルコインとは何ですか?

流動性ファーミングとは何ですか?

Cotiとは? COTIについて知っておくべきことすべて
